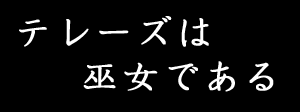
テレーズは明らかな霊媒体質であり、私がずっと描きたいと思っていた「巫女」であった。あまり多くを語ることは出来ないが、『ソドム』にはいくつもの霊的符帳が散りばめられているのである。私たちが実践を繰り返してきた「心霊実話テイスト」とは異なる回路から、私は「霊的」なるものの表出を試みようとした。日本映画史でそうした試みに果敢に取り組んできたのは、言うまでもなく鈴木清順や大和屋竺たち「具流八郎」のグループであり、その一人であった田中陽造脚本の『地獄』は常に基底となる映画であり続けた。あの得体の知れない「カシャッ」という何かが作動する音は紛れもなく地獄から響いてくるものだ。そして原田美枝子が地獄からの母の指令で突き動かされるごとく、テレーズはキャサリンの呼び声によって殺戮へと駆り立てられてゆく。
『ソドム』の登場人物のほとんどは、私が勝手にキャスティングを妄想した「あてがき」なのだが、テレーズ役の小嶺麗奈もまたそうなのであった。というのも私は『ユメノ銀河』を見ていたし、さらにより決定的だったのは『レディ・プラスティック』を見たからなのだ。ある忌まわしい出来事によって封印された伝説的映画の主演女優という、これ以上ないくらい見る者を惹きつけずにはおかぬ設定を受けて、いよいよ画面に姿を現す彼女はまさにその設定にふさわしいオーラを放っていなければならない。そして彼女は本当に画面に現れるなり、それをやってのけていたのだ。ヒロインを襲った悲劇の本源は、彼女自身が放つこの"ただならなさ"にあることを観客に瞬時に悟らせる強さをもって。ヒロインは恋人を思うその心根が一途であればあるほど、思い以上の怪物的領域に突き進まざるを得ず、そして文字通り化けて出る。きわめて先駆的なDV撮りによる低予算映画であった『レディ・プラスティック』は実は「四谷怪談」に最も近づいてしまった映画ではあるまいか‥‥。私は激しく嫉妬するほかなくジタバタ騒いでいたら、友人の根岸洋之プロデューサーがそれを見かねてか、私に小嶺麗奈本人を紹介してくれたのであった。

ひょっとして小嶺麗奈は本当に霊媒体質の人なのではあるまいかと、会う以前に私は少なからず身構えていたのだが、小嶺さん本人は画面で見るのとはうって変わってゲラゲラ笑う屈託のない人で、むろん霊能者ではないのだった。ただ芝居をすると役柄に入り込んでゆくタイプなのでどうしても周囲からはそう思われがちだということだった。で、結果その日の会話は怪談大会になった‥‥。まあ、いかに私が他に何の話題もないかということなのだが。
そんな次第で、私の中では勝手にテレーズという巫女が動き始めたのである。だがまさか本当に、私の勝手なあてがき通り、小嶺さんがこの映画に出てくれるとは思わなかった。いや、小嶺さんのみならず、『ソドム』のキャスティングはほとんどが私の妄想通りに実現してしまったのである。話はそれるが、新谷尚之曰く「何かが憑いてるとしか思えない」異様な強運がソドム撮影隊(高橋組とか監督という呼称は我々スタッフ内で禁止であった)にはつきまとっていた。天候にも信じがたいほど恵まれたのだが、町の炎上するシーンが必要になれば、何故か大工原正樹の『赤猫』がそういう場面を撮っているから同時に複数キャメラを回させて貰ったし、銀行のシーンが必要になれば、万田邦敏の『う・み・め』がまさに銀行のセットを組んでいたのでドサクサに撮らせて貰ったりしたのである。そして我々のクランクアップ後に撮影が開始された塩田明彦の『カナリヤ』では、「もはや超常現象に近い」塩田明彦の雨男ぶりが5月に台風を招き寄せていた‥‥。
いや、すべてを強運と呼んでしまっては、『ソドム』のあの信じ難い現場を縁の下から支えてくれた無数の無言の営為に対して申し訳が立たない。だが、ともかく出演が予定されながら出られなかったのは、撮影当日に救急車で運ばれてしまったアテネ・フランセの松本正道氏と個人的な不幸で我を忘れていた中原昌也の二人だけだったのだ。それはそれで才能というほかないのだが‥‥。
そんなわけで小嶺さんはやって来てくれた。しかしそれでも妄想度の激しい私は、時折真剣に夢の中でもう一つ別の人生を生きたりしかねないので、小嶺さんがこの明らかにわけの判らない、ひょっとしたらすべてが冗談ともとられかねない映画をどう受け止めているか気になって仕方がなかった。そこではじめての顔合わせの時、私はおずおずと「あの何か判らないところありませんか?」と尋ねてみたりしたのだ。言下に「ありません」と鋭い返事が返ってきた。こう書くと何かヤケクソの返事みたいに聞こえるかもしれないが、その声は凛として澄み切っていたのだ。私の迷いはふっきれ、テレーズが何者であるかはすべて小嶺さんに任された。小嶺さんの「役に入り込む」現場での集中力はスタッフを圧倒するものがあった。キャメラの前に立ったトタン、彼女の表情は凄まじい集中によって鋭利に研ぎ澄まされ、「足は速くない」と言いながらその動きは恐ろしく速く見え、何か眼に見えないものを地上に降ろそうとする巫女そのものとなった。唯一苦手そうにしたのは歌う時だけだったが、彼女とキャサリン役の宮田亜紀が声を揃えて「地蔵和讃」や「地獄歌」を歌ったとき、私や助監督の安里は何かが降りてきそうなゾクゾクする身震いを感じていたのである。